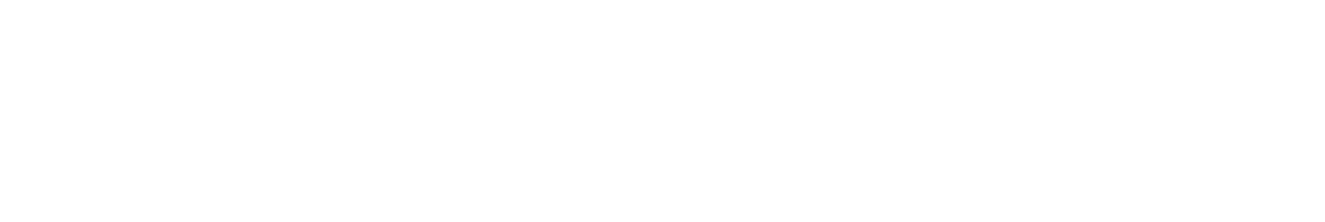快適な家には断熱性能だけでなく、『気密性能』も重要ですが、いったい気密性能とはどういうことなのか、十分に理解できていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
気密性能が高いと家に隙間がほとんどないため、外部から空気が入りにくく、室内の空気も逃げにくい状態となり、快適な空間を少ないエネルギーで作ることができます。そのため、一年中快適な家を建てるためには『気密性能』は欠かせない要素です。
本記事では気密性とは何か、低いと起こる問題や気密性の指標であるC値について解説しています。
また、以下の記事では当メディアが厳選した霧島市でおすすめの注文住宅会社を紹介していますので、気になる方はぜひ一度チェックしてみてください。
気密性能とは『室内の空気を屋外と分ける』性能
気密とは一般的に「空気が出入りできない状態」を指し、住宅でいう『気密性能』は窓や壁などから隙間風が入らない性能を言います。
隙間が少なければ少ないほど気密性は高く、室内の空気が外に漏れにくく外の空気が室内に入りにくいため、一年中快適に過ごすことが可能です。
気密性能は設計段階の計算で求めることはできないため、実際に建物が完成したあと機械を設置して測定し、初めて性能が分かります。
気密性能が低いと起こる問題7つ
気密性能が低いと起こる問題は以下の7つです。
- 光熱費がかさむ
- 空気を効率的に入れ替えできない
- 断熱性能が低くなる
- 外の湿度に左右され結露が起きやすくなる
- 花粉やPM2.5などの浮遊物質が室内に入りやすくなる
- 室内に足音などが響きやすくなる
- 足元が冷えやすくなる
順に解説していきます。
光熱費がかさむ
気密性が低いと外気が部屋の中に入りやすく、逆に冷暖房で調節した空気が外へ逃げやすくなります。
つまり、室内の温度や湿度が不安定になるため、快適な室内環境を保つため冷暖房使用量が増えてしまい、光熱費が上昇。気密性は光熱費のコスト削減に直結する重要な要素と言えます。
空気を効率的に入れ替えできない
気密性が低いと計画的に設置された換気口や換気システムを使っていたとしても、隙間風などによって予想外の空気の流れが発生します。
計画通りの換気が行えなくなると室内の空気が均等に入れ替わらず、室内の一部で換気が不十分になる可能性もあります。
また、気密性が低いと換気システムで入れ替えたい空気の量と、隙間から自然に入れ替わる空気の量とのバランスが崩れ、室内の空気の質が低下しやすくなるため注意が必要です。
断熱性能が低くなる
気密性の低さは断熱性能にも影響します。
建物の隙間から空気が出入りすることによって、断熱材にどれだけ高品質なものを使用していても、隙間から熱の移動が起こってしまうため、断熱性能が十分に発揮されません。
さらに室内外の温度差を小さくするために断熱材は使用しますが、気密性が低いと断熱材の近くにある隙間から空気が流れ込み、断熱材自体の温度が変わりやすくなります。
その結果、家全体の温度管理に影響が出てしまうため、断熱材の効果を十分に発揮させるためには気密性の高さがポイントと言えるでしょう。
外の湿度に左右され結露が起きやすくなる
気密性の低さは断熱性能にも影響を与えますが、断熱性能が下がることによって結露が起きやすくなります。夏場は湿った空気が外から入り込み、冬場では室内の暖かく湿った空気が壁の中へ入り込んだ結果、結露が発生。
繰り返し結露が発生すると、家全体にカビが繁殖し劣化を早めてしまうため気密性を高く保つ必要があります。
花粉やPM2.5などの浮遊物質が室内に入りやすくなる
気密性が低い家は窓やドアの隙間などから花粉やホコリ、PM2.5などの有害物質が含まれている外部の空気が直接室内に入りやすくなります。
さらに、気密性の低い家は効率の良い換気をしづらいため、室内に溜まった有害物質を排出できなかったり、特定の場所に有害物質が溜まりやすくなるなどの弊害があります。
室内に足音などが響きやすくなる
気密性が低く、窓やドア、壁に隙間があると空気と一緒に音も漏れてくるため、外の音が家の中に入りやすく、室内の音も外部に漏れやすい家になります。
また、気密性の低い家は壁や床が振動しやすいため、足音が床に伝わると振動が建材を通して家中に広がり音が響きます。さらに、音が響きやすいだけでなく遮音性能も低下するため音に敏感な方は気密性に注意が必要です。
足元が冷えやすくなる
気密性が低いと床下に断熱材を使用していても、外部から入ってくる冷たい外気により断熱材自体が冷やされ十分に効果を発揮できません。
さらに、床下に入り込んだ冷気は断熱材の上にたまり、床材自体を冷やしてしまいます。
暖房で暖めた空気も気密性が低いことで外部に漏れてしまうため、室内の温度を一定に保つことが難しくなり、床が冷たくなる原因となります。
気密性能を上げるポイント3つ
気密性能を上げるポイントは以下の3つです。
順に解説します。
綿密な設計
気密性を高めるためには、建物の設計段階から気密性を考慮し、綿密な設計をすることが重要。断熱材や気密シートの配置、窓やドアの位置などを気密性能が上がるよう計画的に設計します。
また、家の形が複雑で凹凸が多かったり、窓やドアの多い家は気密性が下がりやすくなるため、単純な形状(正方形や長方形など)の家を建てると気密性を保ちやすいでしょう。
建材の選定
高品質な建材を使用することで、建物全体の隙間を最小限に抑えることができます。
以下の建材は建物の気密性を確保するために使われます。
- 気密シート
- 気密テープ
- シーリング材
- 高気密の窓・サッシ・ドア
- 貫通部用気密カバー
- 防湿気密層
特に各部屋にある窓やドアに気密性の高いものを選ぶと家全体の気密性が向上するでしょう。
適切な測定とメンテナンス
気密性を高めるためには適切な測定とメンテナンスが重要です。
新築やリフォームの際に気密性の測定を行うことで、設計通りの性能が実現されているか確認でき、品質保証としても欠かせません。
高い気密性を保つために定期的なメンテナンスを実施すると良いでしょう。
気密性能で重要な『C値』を解説
C値(相当隙間面積)とは、「家にどれくらいすき間があるのか」を示した数値で、C値が小さければ小さいほど、気密性の高い住宅といえます。
『相当』なのは、隙間の量を測定することで隙間面積を仮説的に示した値なため、実際の面積と完全に一致するわけではないためです。
気密性を高めるためには1棟1棟を丁寧に施工する必要があるため、家づくりにおいて最も判断が難しいとされる『施工精度』を測れる唯一の指標でもあります。
『C値』の基準はあるの?
C値には明確な基準は設けられていませんが、一般的な住宅のC値は10㎠/㎡前後とされています。これは、建床面積が124.4㎡だとすると『C値』は約1,240c㎡、つまり約30×40cmの穴が家に空いているということです。
気密性が高いと謳っている住宅のC値は1.0㎠/㎡以下であることが1つの基準と言われているため、C値は1.0㎠/㎡以下を目指すようにしましょう。
『C値』に関するよくある疑問
C値に関するよくある疑問を集めました。
C値はなんのために必要?
建築した家の気密性能を知るために必要です。
C値はどれくらいが良い?
気密性能が高い家では1.0㎠/㎡以下が良いとされています。
気密性は高ければ高いほどよい?
高ければ高いほどエネルギー効率や室内温度を一定に保つことができます。
一般的な住宅の『C値』は?
一般的な住宅のC値は10㎠/㎡以下と言われています。
『C値』の計算方法は?
C値の計算方法は『住宅全体の隙間の合計面積÷延べ床面』です。
この値が低いと『高気密住宅』で、値が大きいと『低気密住宅』になります。
気密性の高い住まいを建てるならクオリティホームがおすすめ

気密性を重視した住まいづくりを考えるなら、施工実績と技術力に優れた住宅会社を選ぶことが大切です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社クオリティホーム |
| 会社住所(R+house霧島姶良) | 鹿児島県霧島市隼人町真孝25番地 |
| 会社住所(R+house鹿児島南) | 鹿児島県鹿児島市薬師2丁目17番25号 |
| 対応エリア | 鹿児島県 |
| 公式サイト | https://qualityhome.co.jp/ |